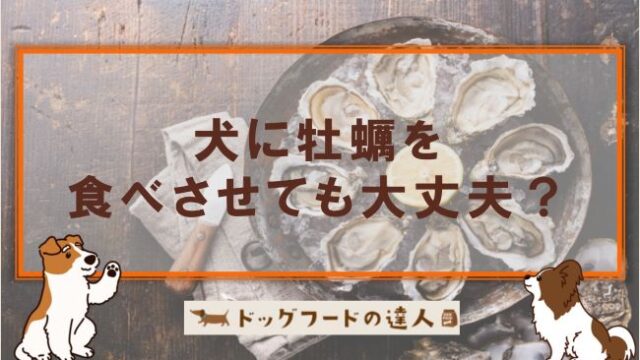愛犬にきなこを与えても大丈夫なのでしょうか? 答えはイエスです。
きなこがドッグフードに含まれていることはまれですが、きなこは身近な食材ですよね。もちなどにきなこをつけて食べたことがあるという人は多いと思います。
なので、愛犬にきなこを与えたいと考えている人もいるのではないでしょうか。
そこで、この記事では「犬にきなこを与えるときに必要な知識」について解説していきたいと思います。
犬にきな粉を食べさせても問題ない
大豆からできているきな粉には、植物由来のタンパク質が豊富に含まれている食べ物です。
きな粉は文字通り、大豆を細かく細粉したものになるので、栄養の吸収効率が良く、ワンちゃんの意への負担も少ないです。
なので、きな粉をワンちゃんに食べさせても問題はありません。
とはいえ、人間用に調理・製造されているきな粉には砂糖が含まれています。
砂糖の量は人間にとっては最適な量ですが、ワンちゃんにとっては、糖分の過剰摂取になりうる可能性があります。
もし、ワンちゃんにきな粉を与える際は、無糖のきな粉を与えるのが無難です。
そもそもきな粉って何?
きな粉は、日本のお菓子などに良く使われている加工食品で、原材料である大豆を細かく粉状にしたものです。
そのため、細粉前の大豆よりも消化・吸収がしやすいという特徴を持っています。
ちなみに、きな粉には、細粉する大豆の種類・状態によって風味が変わってきます。
大豆を加工したきな粉
まず1つ目は、熟成した大豆を細粉して作る「きな粉」です。
スーパーや甘味処などで目にする機会が多い加工食品です。
ちなみに、きなこの語源は「黄な粉」で、黄色い粉という意味です。
黒豆を加工した「黒豆きな粉」
次に2つ目は「黒豆きなこ」です。これは黒豆をいってひいたものです。
黒豆の皮の黒い色素成分のアントシアニンが含まれていて、コクがあるという特徴があります。
ちなみに、アントシアニンには抗酸化作用があります。
青大豆を加工した「うぐいす粉」
そして、3つ目は「うぐいす粉」です。
これは未成熟の大豆である青大豆を原料にしたきなこです。
薄い緑色をしているため、「うぐいす粉」と呼ばれます。
きな粉から得られる効果効能

きな粉の原材料である大豆には、植物由来のタンパク質に加えて、腸内環境を整えてくれる食物繊維が豊富に含まれています。
加えて、ワンちゃんは大豆などの穀物の消化が得意じゃないため、大豆の状態で食べさせても身に含まれている栄養成分の吸収効率が悪いです。
しかし、大豆を細粉してきな粉にしてあげれば、大豆に含まれているタンパク質や食物繊維、そのほかの栄養成分を効率よく吸収できます。
また、きな粉には、食後、急上昇する血糖値を抑制してくれる効果や皮ふ炎、アレルギーの改善や予防にも効果があります。
きな粉に含まれている栄養成分
きなこに含まれている主な栄養素は以下の通りです。
| 成分名 | 成分量(100gあたり) |
|---|---|
| 水分 | 4g |
| たんぱく質 | 36.7g |
| 炭水化物 | 28.5g |
| 食物繊維 | 18.1g |
| 脂質 | 25.7g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 14.08g |
| ビタミンE | 1.7㎎ |
| ビオチン | 31μg |
| カリウム | 2000㎎ |
| カルシウム | 190㎎ |
| マグネシウム | 260㎎ |
| リン | 660㎎ |
| 鉄分 | 8㎎ |
| 亜鉛 | 4.1㎎ |
| 銅 | 1.12㎎ |
| マンガン | 2.75㎎ |
[出典:食品成分データベース(文部科学省)] たんぱく質は三大栄養素のひとつであり、生きていく上で特に重要な栄養素です。血液や筋肉などの体をつくる主要な成分であり、体内で酵素など生命時に欠かせない物質にも変換されます。そして、エネルギー源になることもあります。 炭水化物は脂肪やたんぱく質と並んで三大栄養素のひとつです。犬は人間と比べて必要な炭水化物の量が少ないですが、決して不要なわけではありません。 そして、炭水化物は犬の体内で主にエネルギー源として利用されます。また、すぐ使わない分は体脂肪として蓄積されます。 食物繊維には腸内環境を整える作用があります。具体的には、腸内の善玉菌を増やし、悪玉菌や毒素を排出してくれます。 脂質は3大栄養素のひとつです。細胞膜の成分やホルモンの原料などになっています。不足すると正常に成長できなくなったり、皮ふ炎の原因になったりします。また、油にとけるタイプのビタミンの吸収にも役立ちます。 ただ、とりすぎると肥満や生活習慣病などの原因になってしまうので注意が必要です。 多価不飽和脂肪酸は主に植物油や魚に多く含まれています。そして、酸化しやすいという特徴を持っています。 ビタミンEには抗酸化作用があります。抗酸化作用により、さまざまな病気が予防されます。 カリウムは体内で水分の調整を行っています。体内で増えすぎたナトリウムの排泄を促す働きもあります。また、心臓や筋肉の働きを調節したりする役割も持っています。 カルシウムは骨や歯を形成するために必要不可欠です。また、筋肉を動かすためにも必要です。ただ、過剰に摂取すると逆に骨折などが起こってしまう可能性があります。そのため、適切な量を与えることが重要です。 マグネシウムは体内で骨や歯をつくるために使われています。そして、マグネシウムは体内で不足すると骨から遊離して神経の興奮を抑えたり、エネルギを作ったり、血圧を維持したりするのに利用されます。 85%のリンは体内でカルシウムやマグネシウムと一緒に骨や歯を作る成分になっています。また、15%は筋肉や脳や神経などに存在し、エネルギーを作り出すのに役立ちます。 ただ、リンはとりすぎてしまうとカルシウムを奪ってしまい、骨が弱くなってしまいます。また、腎臓の負担にもなります。 鉄分は血液のヘモグロビンの中に含まれ、酸素を運ぶために必要です。また、エネルギーを作り出すためにも必要です。 亜鉛は体内で作り出すことができないため、食事で摂取する必要があります。 そして、亜鉛には体内のさまざまな働きをサポートして正常に保つ役割があります。具体的には味覚を正確に保ったり、免疫力を向上させたり、新陳代謝を活性化させたり、毛並みや肌の健康を保ったり、抗酸化作用を活性化したりします。 サポニンには体脂肪を減らす効果があります。また、動脈硬化やガンなどの病気を予防する効果もあります。 ワンちゃんの健康維持に貢献しているきな粉ですが、与え方によっては、ワンちゃんの健康に支障を来たす恐れがあります。 ここでは、ワンちゃんにきな粉を与える時に気を付けることを解説します。 きな粉は、大豆を細粉した加工食品です。 原材料である大豆は、小麦や卵などの食材と同じく、比較的アレルゲンになりやすい食材でもあるので、ワンちゃんが大豆アレルギーを発症する恐れがあります。 人間ほど、大豆アレルギーを持つワンちゃんは多くありません。 しかし、シベリアンハスキーやアイリッシュセッター、シャーペイなどの一部の犬種は、大豆が持つタンパク質に耐性がなく、少量でもアレルギーを発症する可能性があります。 少量のきな粉を混ぜたドッグフードを食べて、皮膚を掻いたり、下痢や嘔吐を繰り返すようであれば、アレルギーを発症している可能性があります。 これら症状が診られたら、すぐに掛かりつけの動物病院で診断を受けましょう。 市販品のきな粉の中には、砂糖が入っているモノと入っていないモノの2種類があります。 その中で砂糖が含まれているモノは、ワンちゃんにとって糖分の過剰摂取になる可能性があります。 また当分の過剰摂取によって糖尿病や肥満、歯周病にかかる原因を作る恐れがあります。 あくまで人間が食べることを前提に製造しているので、ワンちゃんにきな粉を食べさせるときは、砂糖が含まれていないモノを少量与えましょう。 きな粉には水分が含まれていないので、賞味期限が切れても腐ることはありません。 しかし、きな粉に含まれている油は、時間経過に伴って徐々に酸化していきます。 酸化が進むと同時に、きな粉が湿気を吸っていれば、カビが繁殖している恐れがあります。 一度封を切ったら、賞味期限は当てにせず、1~2カ月を目安に使い切りましょう。 ワンちゃんにきな粉を与えるときは、大豆アレルギーの発症リスクを加味する必要があります。 その点を踏まえて、どれくらいの量が最適なのかというと、ワンちゃんの体重を基準に分量を調整しましょう。 例えば、体重5kgのワンちゃんであれば、大さじ1/2程度、体重が10kgのワンちゃんであれば、大さじ一杯がベストな量です。 また初めてきな粉を口にする場合は、大豆アレルギーを持っている可能性があるので、これよりも少ない量で与えて様子を伺いましょう。 人間がきな粉を食べるときは、お餅やホットミルクなどの食品にまぶして食べるように、ワンちゃんにきな粉を与える時も、きな粉を何かに混ぜて食べさせるのが無難です。 きな粉を食べさせるのに最適な方法は、普段あげているドッグフードにきな粉を少量混ぜて食べさせるという方法が最適です。 ただし、パグやフレンチブルドッグなど短頭犬種の場合、粉末状のままかけてしまうと気道に入ってむせてしまう恐れがあるので、ドッグフードにきな粉を混ぜる前に、きな粉を少量の水で溶いてから与えましょう。 また、前節でも触れたように、人間用のきな粉を与える際は、無糖のきな粉を与えるようにしましょう。 きな粉をワンちゃんに食べさせるときは、普段あげているドッグフードに少量混ぜる方法で与えるのが無難です。 しかし、飼い主の中には、きな粉を使用した加工食品をおやつに与えたいと考えている方もいます。 ここでは、ワンちゃんに与えてもいいものと与えるべきじゃないきな粉を用いた加工食品を3つ紹介します。 きな粉ミルクは、きな粉と乳飲料を混ぜ合わせたものです。 そして、きな粉ミルクに使われているミルクが牛乳だった場合、犬には与えないようにしましょう。 多くの犬は牛乳に含まれている乳糖を消化することができず、下痢などの原因になってしまう可能性があるからです。 ただ、乳飲料がヤギミルクなど、乳糖が多く含まれていないものであった場合は犬に与えても大丈夫です。 むしろ、きな粉が液体になって摂取しやすくなっているので、きな粉を与える方法としておすすめできます。 きな粉クッキーは犬に与えても問題ありません。 栄養もとれるおやつとして活躍してくれます。 しかし、人間用のクッキーには多すぎる糖分や脂肪分が含まれています。 そのため、人間用のきな粉クッキーを犬に与えるのは良くありません。 犬には、犬用に作られたきな粉クッキーを与えるようにしましょう。 きな粉もちはきなこを使った食べ物としては定番です。 しかし、きな粉もちを犬に与えるのはあまりおすすめできません。 なぜなら、犬は与えられたものを丸呑みにしてしまう傾向があり、もちを大きなまま与えるとのどに詰まってしまう可能性があるからです。 もしどうしてもきなこもちを与えたいなら、小さくカットして与えましょう。 そして、食べている間はのどに詰まらないかどうか、きちんと観察してあげることが大切です。 ワンちゃんに、きな粉を食べさせても問題はありません。 ただし、きな粉単体で与えてしまうと、器官にきな粉が入ってむせてしまうので、普段から食べているドッグフードに少量のきな粉を混ぜ込んだ状態で食べさせるのが最適です。 またワンちゃんの中には、大豆アレルギーを持っている子もいます。 アレルギー発症リスクを軽減するためにも、大さじ1/3~1/2程度のきな粉から与え始めて様子を伺いましょう。 少しでも様子がおかしいと思ったら、すぐに動物病院に連れていきましょう。 ドッグフードの達人では、160種類以上のドッグフードを5点満点で評価したうえで、S〜Eランクでランクづけしています。 最もおすすめなのは、「Sランク」のドッグフードです。 A〜Eランクの商品とも比較したうえで、愛犬にぴったりなドッグフードを見つけましょう。➀たんぱく質
➁炭水化物
➂食物繊維
➃脂質
➄多価不飽和脂肪酸
➅ビタミンE
➆カリウム
➇カルシウム
➈マグネシウム
➉リン
⑪鉄分
⑫亜鉛
⑬サポニン
犬にきな粉を与える時に気を付けること
大豆アレルギーを持っている可能性がある
人間用のきな粉には砂糖が含まれている
与える前に賞味期限を確認すること
犬にきな粉を与える時の適用量
犬にきな粉を与える方法
犬が食べられるきな粉を使った加工食品
きな粉ミルク
きな粉クッキー
きな粉もち
犬にきな粉を与えるときは少量から与えていくこと
Sランクのドッグフードなら… ● ★4.50以上の高得点
● 無添加で穀物不使用
● 栄養バランス◎
● 「獣医師推奨」「ヒューマングレード」など安全なポイント多数
● お得な定期購入あり