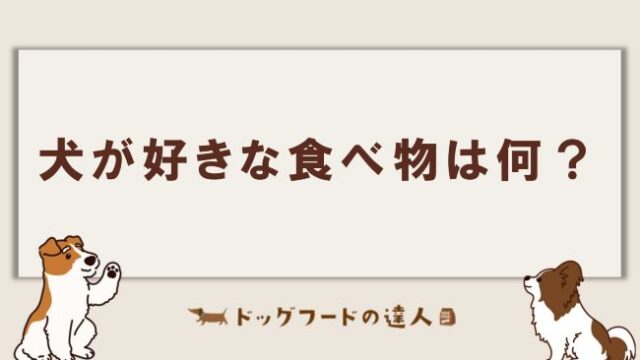ドッグフードには、大きく分けて「目的による分類」「形状による分類」「年齢による分類」があります。
「初めて犬を飼うけど、ドッグフードはどんな種類があるのかわからない」
「愛犬にはどんな種類のフードがいいの?」
そんなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
愛犬のためにも、飼い主としてドッグフードの分類と特徴をしっかり抑えておきたいですよね。
そこで、この記事ではドッグフードの種類と特徴を詳しく解説します。
種類①目的による分類

ドッグフードを目的によって分類すると以下のようになります。
| 種類 | 目的 | |
|---|---|---|
| 総合栄養食 | 必要な栄養素を十分に摂取する | |
| 食事療法食 | 特定の病気を治す | |
| 間食 | 限られた量のみ与える | |
| その他の目的食 | 副食・おかずタイプ | 食いつきをよくする 他のフードや食材と一緒に与える |
| 栄養補助食 | 特定の栄養素を調整する カロリーを補給する | |
それぞれ特徴を見ていきましょう。
総合栄養食
総合栄養食は、「そのフードと水だけで必要な栄養素を十分に摂取できる」というフードです。
日本で総合栄養食の表示をするためには、ペットフード公正取引協議会の定める以下の2つの試験に合格する必要があります。
- 分析試験
栄養成分の基準に合致しているか - 給与試験
必要な栄養が十分摂取できるか
外国産のフードには、「総合栄養食」ではなく「AAFCO(米国飼料検査官協会)の基準をクリア」などの表記をしていることもあります。
食事療法食
療法食は、特定の病気を治すための食事管理で使われるフードです。
獣医師は犬の病気を治すために、食事の栄養の調整を行うことがあります。
ただし、食事療法食は薬ではないため、食事療法食を与えたからといって病気が良くなるわけではありません。
療法食は獣医師からの指示があった場合にのみ与え、指示がない限り与えないようにしましょう。
間食
間食は、おやつやご褒美として、限られた量のみ与えることを目的としたフードです。
毎日食べる主食ではないため、原則として1日当たりのエネルギー所要量の20%以内に抑えることが求められています。
一般には、「おやつ」「スナック」「トリーツ」などと表記されます。
間食には以下のような種類があります。
- 練り加工品
- 素材ベース品
- ガム
- デンタル
- 菓子類
その他の目的食
その他の目的食は、「総合栄養食」「食事療法食」「間食」のどれにも当てはまらず、特定の栄養素を調整したり、カロリーを補給したり、食いつきをよくしたり、他のフードや食材と一緒に与えたりするためのフードです。
以下の2種類に分けることができます。
- 副食・おかずタイプ
副食、ふりかけなど - 栄養補助食
栄養補完食、カロリー補給食、サプリメントなど
種類②形状の分類
ドッグフードを形状によって分類すると以下のようになります。
| 種類 | 形状 | |
|---|---|---|
| ドライタイプ | 水分10%程度以下 | |
| ウエットタイプ | ウェット缶詰 | 水分75%程度 缶詰を使用 |
| ウェットその他 | 水分75%程度 アルミトレー、レトルトパウチを使用 | |
| 半生タイプ | ソフトドライ | 水分25~35%程度 加熱発泡処理済み |
| セミモイスト | 水分25~35% 発泡処理なし | |
それぞれ特徴を見ていきましょう。
ドライタイプ
ドライタイプのフードは、水分が10%程度以下のフードです。 最も一般的なフードで、カリカリと呼ばれることもあります。 種類が豊富であるため、粒の大きさにも様々な種類があることが特徴です。 小型犬には小粒、大型犬には大粒のフードを与えるのがおすすめです。 ウェットタイプのフードは、水分が75%程度のフードです。 水分が多いため、犬が好む本来の生肉の食感に近いのが特徴です。 ただし、レトルトパウチに入っているものは主食になることは少なく、ドライフードに食いつきをよくするために加えられることが多いです。 数日に一回にするなど工夫しましょう。 半生タイプのフードは、水分が25~35%程度のフードです。 半生タイプは、ソフトドライとセミモイストの2種類がありますが、以下のような違いがあります。 つまり、ソフトドライは加熱発泡処理していますが、セミモイストは発泡していません。 どちらのフードも、スプーンでも切れるほど柔らかく食べやすいのが特徴です。 加熱発泡処理を行うソフトドライはふわっと柔らかくなりますが、行わないセミモイストはぎゅっと締まった感触になります。 ドッグフードを年齢によって分類すると以下のようになります。 それぞれ特徴を見ていきましょう。 パピー(子犬)用のフードは、3つの時期によって含む栄養素が異なります。 妊娠・授乳期は、生後4か月までの、まだ離乳していない期間です。 妊娠・授乳期のフードは、フードというよりも母乳の代わりのような粉ミルクや液体のミルクなどが多いです。 幼犬期は、離乳食を食べている期間です。 幼犬期のフードは、粒状のフードではなく、フレーク状や粉末状のもの、ウェットタイプのフードが多いです。 成長期は、離乳食を離れてから1歳になるまでの期間です。 成長期のフードは、成長に必要な高タンパク高カロリーのフードが多いです。 「幼犬用」「成長期用」「グロース」などと表記されます。 アダルト(成犬)用のフードは、種類が豊富です。 なぜなら、アダルト(成犬)期は、成長期が終わってからシニア期に入るまでの期間を表すため、最も対象が広いのです。 「室内で暮らす犬用」「小型犬用」など、犬に合ったフードを選びましょう。 「アダルト」「成犬用」「成犬食」などと表記されます。 シニア犬用のフードは、低脂肪や低カロリー、消化しやすいフードが多いです。 なぜなら、シニア期は運動や代謝の量が減り、睡眠時間が長くなるからです。 噛む力が弱くなっている場合は、ドライタイプのフードをふやかしたり、ウェットフードを与えたりしましょう。 全年齢用のフードは、「パピー(子犬)用」「アダルト(成犬)用」「シニア犬用」の全てに当てはまるフードです。 パピーからシニア犬まで食べられるため、全年齢用のフードを与えている場合は、年齢に合わせてフードを切り替える必要はありません。 「全成長段階」「オールステージ」などと表記されます。 以上、この記事ではドッグフードの種類と特徴について解説しました。 最後にポイントをおさらいしましょう。 ドッグフードを選ぶ時には、どんな種類のフードなのかよく確認することが重要です。 愛犬の年齢や犬種に合ったものを選びましょう。 ドッグフードの達人では、160種類以上のドッグフードを5点満点で評価したうえで、S〜Eランクでランクづけしています。 最もおすすめなのは、「Sランク」のドッグフードです。 A〜Eランクの商品とも比較したうえで、愛犬にぴったりなドッグフードを見つけましょう。
[出典:モグワン]ウェットタイプ
[出典:K9ナチュラル公式通販サイト]半生タイプ
[出典:株式会社ジャンプ]種類 水分量 発泡処理 ソフトドライ セミモイスト 種類③年齢による分類
種類 年齢 パピー(子犬)用 妊娠・授乳期 生後4か月まで 幼犬期 離乳食を食べている期間 成長期 離乳食を離れてから1歳になるまで アダルト(成犬)用 小型犬、中型犬 1歳~約7歳 大型犬 1歳半~約5歳 シニア犬用 小型犬、中型犬 約7歳~ 大型犬 約6歳~ 全年齢用 全ての年齢 パピー(子犬)用
パピー(子犬)用①:妊娠・授乳期
パピー(子犬)用②:幼犬期
パピー(子犬)用③:成長期
アダルト(成犬)用
シニア犬用
全年齢用
まとめ
種類 特徴 目的による分類 総合栄養食 必要な栄養素を十分に摂取する 食事療法食 特定の病気を治す 間食 限られた量のみ与える その他の目的食 食いつきをよくする
他のフードや食材と一緒に与える
特定の栄養素を調整する
カロリーを補給する形状の分類 ドライタイプ 粒の大きさが豊富 ウェットタイプ 生肉の食感に近い 半生タイプ 柔らかく食べやすい 年齢による分類 パピー(子犬)用 ミルクや離乳食 アダルト(成犬)用 種類が豊富 シニア犬用 低脂肪や低カロリー
消化しやすい全年齢用 フードの切り替えの必要がない Sランクのドッグフードなら… ● ★4.50以上の高得点
● 無添加で穀物不使用
● 栄養バランス◎
● 「獣医師推奨」「ヒューマングレード」など安全なポイント多数
● お得な定期購入あり