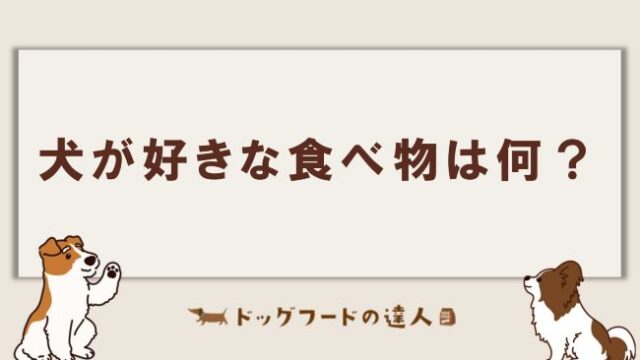「人間と同じように、犬にも味覚はあるの?」という素朴な疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
味覚があるのなら、愛犬が美味しいと感じるものをあげたいですよね。
結論として、犬にも味覚はありますが、人間とは感じ方が異なります。また、シニア犬になると味覚は衰える傾向にあります。
この記事では、犬の味覚について徹底的に解説します。
犬に味覚はあるが人間とは異なる
結論から述べると、犬にも味覚はあります。しかし、人間の味覚とは大きく異なります。
動物は、舌にある味蕾細胞(みらいさいぼう)によって味覚を感じとります。
この味蕾細胞が、人間は5,000個〜10,000個前後あるのに対して、犬は1,700個〜2,000個前後しかありません。
つまり、犬は、人間よりも味覚を感じる力が弱いのです。
犬の感じる味覚と特徴をまとめると以下の表のようになります。
| 甘味 | 最も感じやすく好む犬が多い |
|---|---|
| 苦味 | 感じにくく好んで食べない |
| 酸味 | 2番目に好むがレモンなどの強い酸味は苦手 |
| 塩味 | ほとんど感じられず好まない |
| うま味 | 近年の研究で感じることがわかった |
| 水味 | 水に含まれるイオン濃度を感じ取れる |
犬は味覚よりも嗅覚が発達しているため、エサを食べるときの基準は、嗅覚(匂い)>触覚(舌触り)>味覚(味)>視覚(見た目)なのです。
ここからは、犬の感じる5つの基本味(甘味・苦味・酸味・塩味)を詳しく解説します。
しかし、現在では「味覚地図」は否定されています。
ひとつの味蕾で、すべての基本味を感知することができるとされているのです。
①甘味:好きな犬が多い
犬は、味覚の中で最も甘味を感じやすく、好むとされています。
甘味が含まれているものには以下のようなものがあります。
- 肉や魚に含まれるアミノ酸
- 野菜や果物に含まれる果糖
- 乳製品や母乳に含まれる乳糖
- 砂糖に含まれるショ糖
上記の中でも、肉に含まれるアミノ酸やリノレン酸の甘味を特に好みます。
犬が人間の食べている甘いものを食べたがるのは、肉だけでなく、甘い果物なども食べる雑食として進化したためなのです。
もし犬がフードを食べない場合は、アミノ酸が多く含まれている肉や魚、ヨーグルトなどをドッグフードに少し混ぜて与えてみると良いでしょう。
ただし、犬が甘味を好むからといって砂糖や人工甘味料を必要以上に与える必要はありません。
- ソルビート
- キシリトール
- ビートパルプ
- コーンシロップ
上記のような人工甘味料を摂り過ぎると、歯周病や肥満の原因になるため注意しましょう。
②苦味:感じにくく苦手な傾向
犬は苦味を感じにくく、毒物や危険物だと認識するため、好んで食べないとされています。
これは、犬だけでなく哺乳類全般に言えることです。毒があるものは苦いものが多いため、「苦い=危険」だと認識しているのです。
この習性を利用した、しつけのためのスプレーがあります。
犬の苦手な苦味成分が含まれているため、噛んでほしくないものなどに振りかけることで、犬の噛み癖を防止できます。
③酸味:弱い酸味は好む
酸味は、甘味の次に敏感な味覚です。
弱い酸味は好みますが、強い酸味は好みません。
例えば、ヨーグルトやチーズなどの発酵食品であれば、弱い酸味であるため好みますが、レモンやみかんなど、酸味が強く匂いも強いものは苦手です。
これは、以下のような犬の習性が理由です。
犬は野生動物として生きていた頃、狩りをして食料の肉を得ていました。
一度に食べ切れない肉は土の中に埋めて、後で腐った肉を掘り返して、空腹のときに食べていたのです。
そのため、今でも犬は弱い酸味がある食べ物を好むのです。
④塩味:あまり感じられない
犬は、塩味はほとんど感じられないとされています。
なぜなら、犬が狩りをして他の動物の肉を食べていたからです。
他の動物の肉から血液や体液から塩分を摂取することができたため、塩味に対して鈍感でも困ることがなかったのです。
そして犬は塩味を好まないため、塩分が多く含まれたおやつやジャーキー、スナック菓子などは過剰に与える必要はありません。
⑤うま味:犬も感じられる
近年の研究で、犬もうま味を感じられることがわかりました。
うま味とは、甘味・苦味・酸味・塩味と並ぶ5つの基本味のひとつです。
代表的なうま味には、「グルタミン酸」「イノシン酸」「グアニル酸」などがあります。
⑥水味:水の味がわかる
犬は、人間には感じることができない水味を感じることができます。
水味とは、水に含まれるイオン濃度を感じることができる味覚です。
たとえば、水に塩分がたくさん溶けていればイオン濃度は高くなり、あまり溶けていなければイオン濃度は低くなります。
これは、犬が野生動物として生きていた頃、食べる肉の塩分濃度に合わせて自分の体液を一定に保つために発達したとされています。
シニア犬になると味覚は衰えるが好みは変わらない
シニア犬になると、代謝が落ちたり嗅覚が落ちたりして、味覚も感じにくくなります。
しかし、基本的に好む味は変わりません。
シニア犬になっても最も感じやすく好むのは甘味であるため、食欲などが落ちたら甘味を含むものを加えると良いでしょう。
もし、シニア犬ではないのに食欲が落ちているなど、味覚が衰えていると感じる場合は、心疾患、肝炎、腎不全などの内臓疾患の可能性がありますので、動物病院に連れて行きましょう。
まとめ:犬は味覚よりも嗅覚を重視
以上、この記事では、犬の味覚について解説しました。
最後にポイントをおさらいしましょう。
- 犬にも味覚はあるが、人間とは異なる
- 犬は「甘味・苦味・酸味・塩味・うま味」の5つ基本味に加えて、水の違いがわかる「水味」を感じられる
- エサを食べるときの基準は、嗅覚(匂い)>触覚(舌触り)>味覚(味)>視覚(見た目)
- シニア犬になると味覚は衰えるが、甘味を好むのは変わらない
- シニア犬ではないが味覚が衰えた場合は内臓疾患の可能性
犬と人間の味覚の違いを知り、犬にとって美味しいと感じるものを与えましょう。
ドッグフードの達人では、160種類以上のドッグフードを5点満点で評価したうえで、S〜Eランクでランクづけしています。
最もおすすめなのは、「Sランク」のドッグフードです。
| Sランクのドッグフードなら… |
|---|
| ● ★4.50以上の高得点 ● 無添加で穀物不使用 ● 栄養バランス◎ ● 「獣医師推奨」「ヒューマングレード」など安全なポイント多数 ● お得な定期購入あり |
A〜Eランクの商品とも比較したうえで、愛犬にぴったりなドッグフードを見つけましょう。